郵便番号 596-0805 所 在 地 大阪府岸和田市田治米町460番地 電話番号 072-445-0156 F A X 072-445-0653
岸和田市立山直北小学校
校長室より③
令和6年2月21日(水) 2/20(火))見守り隊の方へ(感謝状とお礼ポスター)
雨の日、暑い日、寒い日、どんな天気の時も、朝の登校時に各町会、老人会、自治会の方、ボランティアの方を中心に、「子どもの安全見守り隊」として朝の車の通行が多い危険な場所に立っていただき、一年間子どもたちが安全に登校できるように見守ってくれています。そのお陰で、今年も子どもたちは安全に登校することができています。本当に有難うございます。2月20日(火)の児童朝会時に、各町老人会の代表の方、自治会の代表の方、有志ボランティアの方(合計19名)をお招きして、体育館で「お礼集会」の時間をもちました。今年はコロナ対応も緩和されたこともあり、5年ぶりに全校児童が体育館に集まった中で実施することができました。第一部では、昨年度に引き続き、8年以上にわたり、朝の見守り活動に参加していただいている方への長年のご尽力に対して敬意を表し、学校園・PTAから「感謝状」を贈呈させていただきました。昨年度は13名の方に、今年度は8名の方に感謝状をお渡ししました。(8名の内、4名が出席されました)

第二部では、児童会代表が見守り隊の皆さんにお礼の言葉を伝えた後、15名の方に子どもたちが作った「お礼ポスター」を贈呈しました。その後、「山直の子の歌」を全員で歌い、最後に見守り隊の方を代表して、連合老人会会長の大井様(岡山町)からご挨拶をいただきました。皆さんご高齢にも関わらず、子どもたちのことを大事に思ってくれているのが伝わってきました。「毎日立ってくれているって当たり前ではなく、本当に有難いことだなぁ…」と感じた貴重な時間でした。

令和6年2月9日(金) 「体力づくり」→→「持久走」「縄とび」に挑戦中!
1月中旬以降、全国的にインフルエンザが流行していて、今も油断できない状況には変わりありません。本校でもたくさんの学級で学級閉鎖を実施していますが、岸和田市内でもインフルエンザによる学級閉鎖や学年閉鎖を行っている学校が沢山あり、感染予防に注意を払いながら日々の教育活動を行っています。1月末から寒波による寒い日が続きましたが、晴れた暖かい日には子どもたちは元気に運動場で遊ぶ姿が見られます。また、3学期は「体力作り」を目的とした「持久走」と「縄跳び」を行っていて、子どもたちは少しでも良い記録を出そうと、一生懸命練習をしています。学校の正門付近を通る機会があれば、外からになりますが、運動場を周回して頑張っている姿や、ジャンピングボードを使って縄跳びに励んでいる姿をみてあげてもらえたらと思います。特に縄跳びは、いつでもどこでも手軽に練習できる体力作りなので、体育の授業時間以外にも、休み時間、放課後などを使って、たくさんの子どもたちが、運動場で自主的に縄跳び練習を行っています。また、子どもたちは自分のレベルにあわせて、今までできなかった「縄跳びのワザ」にも挑戦しています。今までできなかったワザが、一生懸命練習を続けたことで跳べるようになり、「やった、できた」と「成功体験」を通してたくさんの笑顔の花が咲いて欲しいと願っています。平日の夕方や休日の日などに、家でも練習をしたいから縄を家に持ち帰り、練習をしている姿を見かけた時、子どもたちのできる技を見てあげて下さい。そして、可能なら、学校が休みの日に、保護者の皆さんとお子さんが一緒に縄とびをする時間を共有されてはいかがでしょうか?保護者の皆さんは昔のように軽快に跳べないかもしれませんが、保護者の方が昔に習得した「縄跳びのワザ」を思い出しながら、一緒に縄とびをする時間を持てたら、家族の絆が深まる時間になるのではないかと思います。

令和6年1月25日(木) 【山北まつり】話合い(企画)→準備→当日の役割り→片付け 等の経験を通して
この冬一番の寒さの中、子どもたちの笑顔がたくさん見られた【山北まつり】そもそも 【山北まつり】とは・・・ですが、1・2年生はお客さんとして3年生~6年生が準備してくれたお店を回り、3年生~6年生はクラスの半分の人がお店の当番で、残りの半分の人がお店を回り、時間で交代をします。どのお店も工夫を凝らしたすばらしい内容のお店ばかりで、子ども達の発想の豊かさには感心させられました。各クラスで、「来てくれた人に楽しんでもらえるよう、どんなことをしよう・・・」という話合いから始まり、当日までの段取りや準備、当日の一人ひとりの役割、そして最後の片付け等、どの役割も子どもたちにとっては貴重な体験でした。当日、廊下で出会った児童に「楽しい?」と聞くと、全員が「寒いけど、とても楽しい」と、笑顔で返事をしてくれました。楽しい時間が終わった後は、「自分の役割をきちんと果たし、たくさんの人がお店に来てくれ、やって良かった」と、やり遂げた達成感が満ちていました。自分たちで企画運営をした今回の「山北まつり」を通して、楽しかっただけではなく、それぞれが自分の持ち場をやり切ったことで、心も大きく成長したのではないかと思います。

1/17 事前予告なしの地震想定避難訓練を実施
地震は、 いつ、どこで起こるかわからないので、今回はいつ避難訓練をするかを予告せずに行いました。お正月に起こった「能登地震」をテレビ等でみているので、本当の地震の怖さを感じながらの訓練になりました。建物の中にいた児童は身を低くして頭を守る行動をとり、運動場にいた児童は建物の倒壊にそなえて運動場中央に集まっていました。

令和6年1月9日(火) 新年あけましておめでとうございます。能登半島地震と航空機の衝突事故より
本年も子どもたちの健やかな成長を願って、家庭の保護者と学校の保護者(教職員)が同じ方向をむいて頑張りますので、よろしくお願いします。 さて、新年がスタートして9日経ちましたが、1月1日に「能登半島地震」、2日には「日本航空と海上保安庁の航空機の衝突事故」が起きました。29年前の1995年1月17日午前5時46分に「阪神淡路大震災」が起きた時、亡くなった方の多くが、家屋倒壊による圧迫死、窒息死、火事による焼死などで、負傷者の多くが家屋や転倒した家具の下敷き、室内の落下物によるケガでした。また、非難している人が1番困ったのは、飲み水や水が足らない、電気やガスが使えない…等、日ごろ当たり前に使っていた物がないという問題でした。その時の教訓を受けて、災害に対して、日頃から備えることの大切さがずっと言われています。私も今回の地震後に、改めて自宅にある防災グッズ(水の備蓄、ラジオ、懐中電灯、電池、乾パンやカップ麺等の日持ちのする飲食物、カセットコンロなど)を再確認してみました。また、航空機の衝突事故では、日航機が着陸後に機体が炎上している中、着陸後18分間で379人全員が無事脱出できたのは、日頃の訓練の成果を生かした客室乗務員(CA)の臨機応変で、冷静な判断があったからと言われています。学校でも、火災や地震想定の「避難訓練」、そして、大災害時に保護者の方に子どもを引取りに来ていただく「引渡し訓練」等、大切な子どもの命を守る為に災害時想定の訓練を行っています。そして、実際に災害が起こった時に、大人も子どもも、一人ひとりが自分で冷静に判断し、適切な避難行動を取れることが、大切な命を守る第一歩であると思います。家にいる時、外出時、登下校時など、いつどこで災害が起こるかわかりません。子どもが災害にあった時、どういう行動を取るべきか、また自宅の災害への備えは大丈夫か…等について、今一度、子どもを含めた家族全員で話をする時間を取って頂けたらと思います。
令和5年12月22日(金) 2学期、様々な場面でご理解・ご協力有難うございました
終息はしていませんが、新型コロナ感染が一息ついたと思ったら、インフルエンザの感染予防に追われながら、保護者の皆さんと地域の皆さんに支えていただきながら2学期を過ごしたように思います。全校児童が一堂に会した「運動会」では、子どもたちの笑顔のために、PTA実行委員さん・学年代表さん・学級委員さんには精力的に動いていただきました。また、毎日子どもたちの登下校を見守っていただいた地域の見守りボランティアのみなさん・交通指導員さん・更生保護女性会と民生児童委員さんなど、本当にたくさんの方の見守りのおかげで、2学期を無事終了することができました。本当に有難うございます。12月に入りインフルエンザの感染が増加傾向にあり、年末年始も感染予防に留意しながらの生活を余儀なくされそうです。来たる2024年こそ、日々感染症に注意を払う必要がなくなり、安心して日常生活が送れるようになって欲しいと願っています。最後になりますが、子どもたちが楽しみにしている大きな行事(運動会をはじめ、修学旅行、色別音楽会、学習参観、秋の遠足など)を無事終了することができたのも、保護者の皆さんが家庭内感染を起こさないよう気配りをしながら毎日の生活を送り、子どもに感染しないよう予防して頂いているおかげと感謝いたします。この冬休みも引き続き家庭内感染予防には留意して頂きながら、子どもたちにとって、笑顔があふれる楽しい冬休みになることを祈っています。そして、来たる2024年(たつ年)が保護者の皆様にとって、そして山直北小学校の子どもたちにとっても、素晴らしい1年であります様に願っています。
2024年は辰(たつ)年
「辰」は十二支の5番目で、「振るう」という文字に由来しており、自然万物が振動し、草木が成長して活力が旺盛になる状態を表します。天高くのぼる龍のように、辰年には「運気の上昇」「景気が上向く」などといった言い伝えもあるようです。辰年が、皆さまにとって「運気や景気が上昇する1年」であります様に!
令和5年12月19日(木) 「平和」の大切さを、6年生が下級生に伝承!
1・2学期を中心に6年生が取り組んできた「平和学習」。「平和」からイメージを広げ、そこから出た疑問や知りたいことを、まず本やタブレットで調べる個人の活動からスタートしました。そして、次に、調べただけではわからないことを知る為に、世界で初めて原子爆弾を投下された「広島」から「被爆体験伝承者」の方に来ていただき、聞き取り学習を行いました。更に、自分たちが住む「大阪」での被害を知るために、「ピース大阪」に社会見学に行き、戦争の恐ろしさについて学びました。この「平和学習」を通して、戦争の悲惨さ、平和の大切さに気づくと共に、今の社会情勢に目を向け、平和な社会を築いていくために、今自分たちにできることが何かを考えました。そして12月15日(金)朝の時間、下級生の教室に行き、6年生一人ひとりがタブレットを使いながら、学んだことと、今できることを伝えました。

さるに要注意! 近隣でかなり出没しています
日曜日朝、保護者の方から「8時頃、三田町のラムー付近に猿が出没しました。」という連絡をいただき、全家庭にその旨のメールを送信しました。先週の金曜日は流木町(流木墓地)で、この月曜日は稲葉町や積川町で同様の猿の目撃情報が寄せられています。食べ物を探しに人里に来ている可能性が高いと予想されます。お家でも、猿を見かけた時は次の4点に注意するよう、子どもたちへのご指導よろしくお願いします。
① 猿に決して近づかない ②猿と目をあわせない ③ 猿に食べ物を見せない ④ 食べ物(エサ)を与えない。家の周りにエサになるような物を置かない
令和5年12月6日(水) 家庭学習「継続は力なり」日々の積み重ねを大切に!
① 家族の協力で、「環境づくり」を大切にしてあげて下さい
家庭で学習する時間を「宿題」+「自主学習」する時間と考え、子どもたち一人ひとりに「学習習慣」を身につけさせ、わかる喜びや楽しさを味わえるようになれば、学習意欲や自信が高まります。「自主学習」は何か特別な学習をするのではなく、復習や予習をする時間と考えたらいいと思います。家庭学習を定着させるには、「学習に集中できる環境づくり」が大切です。例えば、①始める時間を決める ②学習する場所を決める ③テレビ等を消し、机等の上を広くしてから始めるなど……家族の協力が必要になってきます。毎日の予定にあわせて、集中して学習できる時間を整えましょう。
② ほめる・見守る・励ますことで自信がつきます
子どもたちの家庭学習に目を通してあげ、◎自分で家庭学習をしたこと ◎計画通りにしたこと ◎継続したこと 等をほめたり、励ましたりすることで自信を持たせ、やる気を引き出しましょう。小さな変化でも積み重ねれば、大きな変化です。
上記①②を実行する → 家庭学習の効果(良さ)が表れます
・子どもの理解度がわかります ・家族のふれあいや会話の機会が増えます ・学習習慣が身につきます ・学習意欲や自信が高まります
・脳が活性化します ・計画的にする力(予習復習)がつきます ・学校で習ったことを忘れません ・学力、考える、工夫する、創造する、追及する力がつきます
・約束を守る力(するべきことをする力、決めたことをやり遂げる力)が育ちます ・テレビやゲームの誘惑に負けない力・我慢する力がつきます
・根気や自分をコントロールする力がつきます
令和5年11月24日(金) 学校と家庭が同じ方向を向いて、子どもの「自己肯定感」を高める声かけを、日々意識して実行していきましょう!
2学期はじめの校長室通信でもお知らせしましたが、1学期に実施した「学力テスト」(3年~6年)の結果、「学校に行くのが楽しい」「先生は貴方の良いところを認めてくれている」「友達と協力するのは楽しい」等の回答が平均より高かった反面、「自分には良いところがあると思う」という回答が、平均より下回っていました。これは子どもたちが「自分に自信がない」と感じており、注意されたり怒られたりする機会が多い反面、ほめてもらったり感謝されたり、自分に自信を持てるような機会が少なく、「自己肯定感」(ありのままの自分を好きになる気持ち)が低いと言えます。我々大人でも「有難う。〇〇してくれて助かった」「今日のご飯とても美味しいよ。有難う」と言われたら、「やって良かった。また明日も頑張ろう」と嬉しい気持ちになります。子どもは大人からほめられたら「自分のことをほめてくれた。次も頑張るぞ!」という気持ちになります。私たち大人も自分が子どもの頃、「お父さんやお母さんがほめてくれて嬉しかった。そして、次も頑張ろうと思った」という経験があると思います。その反面、保護者の方から「自分は子どもの頃、親からほめられたことがなかった。だから、自分の子どもにどんな声かけをして、何をほめたらいいかわからない」という声を聞いたことがあります。子どもが手伝いをしてくれたら、「手伝いをしてくれて有難う。お母さんはうれしいよ」と、お母さんのうれしい『気持ちを伝える』声かけで十分です。子どもが間違ったことをした時は厳しく叱るが、それ以上に、日々ほめ言葉や有難うのプラスの声が飛び交う家庭には、沢山の笑顔と温かい空気が漂っていると思います。
【Q1】「自己肯定感」って、どういうこと?
漠然としたイメージは浮かんでいるのではないでしょうか?「自分を大切にする気持ち」「他者と比べることなく、ありのままの自分を好きと思える気持ち」のことを言い、「自己肯定感」は誰でも高めることができます。
【Q2】どうすればいいの?
◎まず、子どもに様々な「ありがとうの言葉」「ほめ言葉」を伝えましょう!
【Q3】「自己肯定感」が高いと、いいことがあるの?
◎折れない心・たくましい心が育ちます。また、自信をもって物事に取り組むことができ、自分の周りの人のことを大切に思うようになります。
【Q4】「自己肯定感」が低いと、どうなるの?
◎自信を持てなくなったり、不安感が強くなったりします。 ◎人間関係の構築が難しくなる場合があります。
【Q5】子どもへの接し方の具体例(言葉や思いに寄り添う)
《例》子どもが食事のお手伝いをしてくれた時(具体的に伝える) → 〇〇ちゃんが、お皿を出してくれて助かるよ、ありがとう。
《例》普段のコミュニケーションの中で、子どもの存在を認める → 〇〇ちゃんのこと、大好きだよ。(はっきりと思いを伝える)
《例》食事中の会話で(親自身の思いを伝える)「今日の給食、苦手な野菜も食べて完食できたよ」→「野菜も食べたんや!よく頑張ったね。お母さん、うれしいな」
《例》お風呂の湯舟の中で「今日、鉄棒で前回りができたよ」→「頑張ったね。すごいね」
【Q6】「怒る」と「叱る」の違いは何でしょうか?
◎「怒る」は感情的に自分のイライラや怒りをぶつけるもの→自分のために ◎「叱る」は相手のためを思い、アドバイスをしたり注意したりするもの
◎子どもの成長のためには、「叱る」ことも大切です。
【Q7】子どもが言うことをきかない時の「叱り方」の具体例
◎「ゲームをやめなさい」「後片付けをしなさい」など、何回言っても言うことをきかない子どもにイライラして、「いつまでやってるの!さっきから何回も言っているのに!いい加減にしなさい。もう終わりなさい」と、大声を張り上げたあとで、「しまった!」と思ったことはありませんか? → これは「怒る」です
◎「目が悪くなるから、もうやめなさい!」「時計の針が「9」までね。「9」になったら、お母さんと一緒に勝負して、おしまいにしよう」 → これは「叱る」です。頑張ったことをほめられ、認められた時に「自己肯定感」は育ちます。最後はお家の人と勝負して、きちんと『おしまい』ができた時は、「えらかったね!」と、一言ほめてあげましょう。
◎叱る場面では、ぜひ「叱っている理由」をお子さんにしっかりと伝え、「あなたが大好きだから、言っているんだよ」と一言付け加えてあげるだけで、子ども自身も「いつも私ばかり・・・」ではなくて、「私のために言ってくれているんだ」=「自分は大切にされている」と感じることができます。
◎叱られることは、子どもたちにとって悪いことだけではなく、成長できるチャンスです。
令和5年11月10日(金) 【JAFの自転車事故の実験より】・・・歩行者は頭などに強い衝撃
山直北小学校の校区は、細い路地が多く、自転車と人(特に、幼児・児童・高齢者)との接触事故が、いつ・どこで起こっても不思議ではありません。特に最近は、スピードの出し過ぎやスマホ等を操作しながら自転車を運転している人が多いように思います。「スマホに夢中になり、歩行者がいることに気が付かなかった」という事故を起こさない為にも、スマホを操作しながら等の危険な運転をせず、周りに気を付けて、事故のない様に心掛けてほしいと願っています。
◎JAF(日本自動車連盟)が行った実験は、歩行者に見立てた人形に、時速 20kmの速さの自転車を正面から衝突させて行われました。人形は衝突の反動で押し出されて腰から地面に倒れ、その後、頭を強く打っていました。JAFの担当者は「歩行者は通常ヘルメットを着用していないので、自転車に衝突された場合、頭部に致命傷を負ってしまう可能性が高く、命に関わる重大な事故につながりかねない。自転車による事故の場合、その多くが交差点などでの出会いがしらの衝突なので、信号や一時停止など基本的な交通ルールを守ることで事故は減らすことができる。自転車の利用者は増えているので、ルールを守った運転を徹底してほしい」と話しています。
大阪府では、自転車利用者が歩行者との接触事故を起こし、損害賠償責任を負った場合の経済的負担の軽減と被害者の保護を図る為、平成28年7月1日から「大阪府自転車条例」を施行し、「自転車を運転する者は、必ず自転車保険に加入する義務がある」と加入を義務化しています。このような「自転車と歩行者の事故」の損害賠償裁判の判決事例を見ると、損害賠償額が9,521万円と高額になったケースもあります。万が一、自転車事故を起こしてしまった時に備え、今一度、各家庭で自転車損害賠償保険に加入しているかの確認をお願いします。(今、加入している車等の保険に自転車損害賠償保険が付いていることがよくあります)自転車は、自動車と同じで道路交通法では車両の仲間です。(※道路交通法では、13歳未満の子ども、大阪府自転車条例では65歳以上の高齢者に対し、ヘルメットの着用を求めています。義務ではありませんが……)
令和5年11月1日(水) 10/27(金)~28(土) 6年生伊勢志摩方面への修学旅行
長年、山北の修学旅行は広島でしたが、「現地で発熱や病院へいく児童がでて、保護者の方のお迎えが必要な時、車で片道6時間かかる広島まで来てもらうのは申し訳ない」との思いで、2年前から伊勢志摩に行先を変更しました。子ども達は修学旅行に行ける喜びと、たくさんの人に感謝の気持ちを持ちながら、2日間の集団行動を通してたくさんの大切なことを学んだことと思います。1日目は、楽しみにしていた「スペイン村」、アトラクションを思いっきり楽しみ、その後ホテルに到着。昼に岸和田で降った雨が伊勢にやってきたのが、ちょうど夕食中でした。ホテルは海のそばにあり、心地よい波音を聞きながら熟睡しました。2日目の日の出前5時45分、部屋の窓から水平線の彼方に「富士山」の頂上が見えるかもしれない…と期待していたのですが、残念ながら水平線に雲がかかっていて見えませんでした。その後、水平線から昇ってくる太陽を見ながら海辺の散歩を楽しみました。2日目の午前中は「鳥羽水族館」でたくさんの海の生き物とふれあい、昼は「おかげ横丁」で楽しい時間を過ごしました。「あかん、もうフラフラや!」と言いつつ、色々な乗り物にチャレンジしたスペイン村。「何を買って帰ろうかな?」とあげたい人の喜ぶ顔を想像しながら、悩みながら選んだお土産。友だちと寝食を共に過ごしたホテルでの楽しい時間…など、全ての思い出が一人ひとりの『一生の宝物』になったことと思います。最後になりましたが、今回の修学旅行に全員が参加でき、無事実施できたのも、保護者の皆さんが「祭礼時、インフルエンザが流行していたので、自分が感染したら子ども達に迷惑がかかるので、予防をしっかりやろう。」というご協力があってのことと感謝申し上げます。本当にありがとうございました。


令和5年10月20日(金) 園芸委員会が稲刈り体験 → だてがけ体験 → ・・・
毎年6月に浅田先生が校庭の一角に「水田」を作ってくれ、児童が「田植え体験」を行っています。山北校区でも昔は田んぼだった場所に家が建ち並び、農業に従事している方が減少しています。子ども達が身近でお米の一生(苗を植え、お米ができ、ご飯になるまで)を知る機会が減ってきており、市内では山北をふくめ数校がこのような田植え・稲刈り体験を行っています。今年は、6月の田植え体験で園芸委員会の児童が1人2~3株の苗を植えました。10月祭礼が終わる頃になると立派な大きな株になり、稲穂も頭を垂れるくらい実りました。そして、19日(木)に浅田先生から鎌の持ち方、稲のつかみ方、刈り方を教えてもらいながら「稲刈り体験」を行いました。初めて鎌を手にした児童もいて、慣れない手つきながら、怪我なく稲を刈り終えました。中には「お家で稲刈りの手伝いをしたことがあるの?」と思うくらい稲の株を上手に束ねて持ち、素早く鎌で稲を刈っている手慣れた児童もいました。ただ、作業を見ていた低学年の児童の中には、「これって何?これからどうなるの?」と毎日食べているお米がこのような作業を経て、食べることができていることを知らないことに、少し驚かされました。何事も経験することって大事だな…と思いました。そして、刈った稲は直ぐに「だてがけ」(場所により「はざがけ」とも言います)をして、湿度の低い秋の日差しの下で天日干しをしています。「だてがけ」とはお米を干すことで、アミノ酸と糖の含有量が高くなり、また、稲を逆さまに吊るすことで、わらの油分や栄養分、甘みが最下部の米粒へおりて、栄養とうま味が増すと言われています。ひと昔前は、田んぼにこのように刈り取った稲を吊るしている光景をよく見かけましたが、今は刈り取った稲をすぐに乾燥機に入れるお家が増え、だてがけをしている田んぼをあまり見かけなくなりました。校庭でしっかり乾燥ができたら、次は千歯扱き(せんばこき)という昔ながらの農機具を使って、もみだけを落とす「脱穀(だっこく)」をします。そして、最後は、自分たちで作ったお米を使って、どんな美味しいごはんになるか、今から楽しみです。


令和5年10月18日(水) 10/15運動会 『感動』という『宝物』を届けるために
土曜日夕方から日曜日の朝方まで本降りの雨になり、日曜の朝5時すぎに学校に着いたら、運動場にはかなりの水が浮いていました。「日曜日しか来れない保護者もいるし、子ども達もお家の人に見てもらいたいと思っている。天気は回復に向かっている予報なので、少しでも良いグランド状態にして演技をさせてあげたい」との思いで、教職員によるグランド整備がスタートしました。校舎内の廊下の電気をつけて明るさを確保しながら、テントの移動、水取り、土入れ、ライン引き、本部や放送機器の設営……と予定の20分遅れで何とかスタートすることができました。教職員の思いが通じたかのように、子どもたちは一生懸命素晴らしい演技を見せてくれ、世界に一つしかない『感動』という『宝物」をお家の人に届けてくれたと思います。特に小学校最後の運動会になる6年生は、演技・応援・係り活動等すべてにおいてリーダーシップを発揮し、下級生の良き手本となり、全校児童を引っ張ってくれました。5・6年生の演技を見た下級生は「自分も高学年になったら、あんな演技ができるようになりたい」と憧れを持ったことと思います。また、PTA役員・実行委員・学級委員の皆さんには、早朝からご協力いただいたおかげで、無事運動会を終えることができました。本当に有難うございました。

次年度への反省として・・・・・・
今年の運動会、反省点が2点あります。1点目は『カメラゾーンには名札を付けた方のみ入れる』というルールをほとんどの方が守ってくれましたが、一部シールを付けた方がカメラゾーン入っていて、注意しても動いてくれませんでした。2点目は正門から入ってすぐ左手の所や体育館に通じる通路に、浅田先生と子どもたちが大切に作っている学年の畑や花壇があります。その畑や花壇に幼子のくつ跡、大人のくつ跡がたくさんあり、せっかく芽が出てきていた作物を踏み荒らしてしまっていました。毎朝子どもたちが水やりをしているおかげで芽が出てきて、「今後の成長を楽しみにしていたのに……」と子どもたちも教職員も悲しい思いをしました。以上2点を次年度に活かして頂けたらと思います。
令和5年9月29日(金) 日曜参観、PTA学年行事への参加 有難うございました。
全国的にインフルエンザや新型コロナが大流行しているのをうけて、保護者の皆さんにもマスク着用や手洗い等の各自のできる感染対策をお願いながら、日曜参観とPTA学年行事を実施しました。今年から保護者の方の人数制限をなくして実施しましたが、マスクの着用等のご協力をいただきながら、無事終了することができました。子どもたちも保護者の方に見てもらえるということで、緊張しながらも一生懸命な姿を見てもらいたく、いつも以上に頑張っていたように思います。また、参観後に4年ぶりに行った親子学年行事では、子どもたちと家族の方が一緒に楽しむことができました。学級委員さんには準備から片付けまで大変お世話になり、有難うございました。
コロナ・インフルエンザ感染に注意!
ニュースでも報道されているように、全国的にインフルエンザ感染者が急増しています。岸和田市内でも9月16日・17日のだんじり祭りが直接影響しているのかどうかはわかりませんが、海側に近い学校で学校閉鎖、学年閉鎖、学級閉鎖が相次いでいます。山北も含めた山手地区は10月1日に試験曳き、7~8日にだんじり祭りがあります。そして、祭礼が終わって1週間後の15日(日)には「運動会」があり、27日(金)~28日(土)には6年生の修学旅行があります。各自でインフルエンザとコロナの感染対策をした上で、感染の広がりがない楽しい祭りであって欲しいと願っています。(私も自町のだんじり祭りに関わっていて、感染予防には注意します)学校では、すでに運動会に向けての学年練習が始まっていて、子どもたちは本番の成功を目指して一生懸命頑張っています。運動会当日、インフルエンザやコロナ感染で出場できない子どもが一人もなく、全員が練習の成果を力いっぱいの演技ができる様にする為にも、ご家庭でも、その場面・場所に応じた感染予防について、ご理解・ご協力をお願いします。


令和5年9月26日(水) ~ 先日、配布した「全国学力学習状況調査」の結果より ~ 継続は力なり『毎日、家で学習する習慣』を身につけ、『学習したことの定着』を図っていきましょう!
【課題②】「学校の授業以外に、普段1日当たり、どれくらいの時間、勉強をしますか?」(学習塾での学習時間、家庭教師との学習時間、インターネットを活用して学ぶ時間を含む)という質問に対し、「平日は1~2時間以上する」と回答した人が約18%(全国平均は約32%)で、「全くしない~30分未満」と回答した人が約42%(全国平均は約16%)いました。
この結果は本校だけの話ではなく、岸和田市内の全小学校に共通しています。本校と全国を比較してみると、「平日は1時間以上する」が本校では約32%に対し、全国平均では約57%あり、約25%の差がありました。また「平日に勉強を全くしない」人は、山北が約25%に対し、全国平均が約5%でした。これは学校で学習した時には理解できていても、家でほとんど学習をしていなければ、せっかく学習して理解できたことが頭の中に残らず、時間が経つにつれ忘れていってしまっている状態であるといえます。元プロ野球選手で、日本プロ野球と大リーグで活躍したイチロー選手が、「『努力』せずに何かできるようになる人を『天才』というのなら、僕はそうじゃない。『努力』した結果、何かができるようになる人のことを『天才』というのなら、僕はそうだと思う」と言っています。「継続は力なり」という言葉があるように、毎日コツコツと、地道な『努力』を積み重ねていくことが、やがては大きな力になり、やがては実を結ぶことになります。今まで、ほとんど家で勉強をしたことがないお子さんは、「勉強しなさいと言うけれど、どのように勉強をしたらいいのかわからない」と思っていることが多いようです。子どもの横に保護者の方が一緒に座って、アドバイスをしながら一緒に学習を進めていく等のご協力をいただきながら、子どもが頑張った時には、「よく頑張ったね!」と、言葉に出して目いっぱいほめてあげていただけたらと思います。保護者の方からのほめ言葉こそが、「明日も頑張ろう」という子どもが頑張れる気持ちの原動力になります。保護者のみなさんのご理解・ご協力よろしくお願いします。 「継続は力なり」です
令和5年9月21日(木) ~ 先日配布した「全国学力学習状況調査」の結果より ~ 子どもたちの「自己肯定感」を高める声かけを、学校と家庭が同じ方向を向いて、継続してやっていきましょう!
【課題①】「自分には良いところがあると思いますか?」という質問に対し、「ある」と答えた児童が、全国平均より少し少なかった。
4月に実施した「学力テスト」(3年~6年)の結果と考察を先日配布しました。「学校に行くのが楽しいか」「先生はあなたの良いところを認めてくれているか」等が全国平均より高かった反面、「自分には良いところがあると思うか」という回答が79%で、全国平均84%より下回っていました。これは昨年に比べて全国平均にかなり近づきましたが、「自分に自信がない」ことを表しており、注意されたり怒られたりする機会が多い反面、ほめてもらったり感謝されたり、自分に自信を持てるような機会が少なく、「自己肯定感」(ありのままの自分を好きになる気持ち)が低いと言えます。我々大人でも「有難う。〇〇してくれて助かった」「今日のご飯とても美味しいよ。有難う」と言われたら、「やって良かった。また明日も頑張ろう」と嬉しい気持ちになります。子どもは大人からほめられたら「自分のことをほめてくれた。次も頑張るぞ!」という気持ちになります。私たち大人も自分が子どもの頃、「お父さんやお母さんがほめてくれて嬉しかった。そして、次も頑張ろうと思った」という経験があると思います。その反面、保護者の方から「自分は子どもの頃、親からほめられたことがなかった。だから、自分の子どもにどんな声かけをして、何をほめたらいいかわからない」という声を聞いたことがあります。子どもが手伝いをしてくれたら、「手伝いをしてくれて有難う。お母さんはうれしいよ」と、お母さんのうれしい『気持ちを伝える』声かけで十分です。子どもが間違ったことをした時は叱るけれど、それ以上に、ほめ言葉や有難うの声かけが飛び交う家庭には、沢山の笑顔と温かい空気が漂っていると思います。
令和5年9月13日(水) 9/12(火) 地震と火災を想定した避難訓練を実施
9月1日は「防災の日」で、全国各地で有事に備えた訓練が行われました。山北でも、9月12日の2限目に避難訓練を実施しました。地震の揺れがおさまり、避難の指示が出てから、「お・は・し・も」の合言葉を思い浮かべながら、「押さない・走らない・しゃべらない・戻らない」を意識し、運動場に整列しました。避難訓練の様子を見ていた消防署の方から、「しゃべらずに避難する姿は、とても良かった」と、お褒めの言葉をいただきました。そして、その後、消防署の方から「火事の時は、煙を吸ってしまい、死亡することが多いので、ハンカチやタオルで口や鼻を覆い、低い姿勢で逃げること(煙は部屋の上からたまり、下に広がっていくので)が重要です」と教えていただきました。私からは、「学校や家で大人がいる時に地震が起こったら、〇〇〇しなさいとすぐに指示をしてくれるけれど、大人がいない場所で地震が起こったら、自分で考えて行動をしないといけないことを話ししました。特に、ららぽーとなどの大きな商業施設に行った時に地震が起こったら、電気が消え、真っ暗になってしまう。その時は緑色の「非常口」(左記)を目指して、低い姿勢でハンカチやタオルで口や鼻を押さえながら、自分で考えて逃げることが大事」という話をしました。地震が起こった時に備え、家族全員で家の中や通学路等の危険個所を再確認する時間を持っていただけたら幸いです。


令和5年9月7日(木) 9/5(火) 5年生対象に非行防止教室を実施
例年「規範意識の醸成」を目的に、5年生を対象に「非行防止教室」を行っています。今年も9月5日(火)の3限目に岸和田少年サポートセンターの青少年健全育成推進員の方に来ていただき、紙人形劇を交えながら身近に起こっている「万引き」「暴力」「不審者」「いじめ」「スマホの危険性」等の話を聞きました。「万引き」は一度やってしまうと罪悪感が薄れ、次もやってしまう可能性が高い犯罪行為で、見張り役も共犯であることや、見つかるとお店から警察へ通報され、保護者が警察へ引き取りに行くことになり、家族にとても悲しい思いをさせる行為であること。「暴力」行為は暴行罪・傷害罪という犯罪行為であることを学びました。そして、①社会ルールを守ることの大切さ ②自分で心のブレーキをかけることの大切さ ③被害者や家族の気持ちを考えること(思いやりの気持ち)の大切さ ④犯罪行為を手伝ってはいけないことの大切さ ⑤非行に誘われた時、勇気を持って断ることが大切さについて教えていただき、子ども達はしっかり話を聞いていました。子どもたちは学年が上がるにつれて、色々な情報を耳にし、大人の知らないところで非行行為への誘惑があったり、スマホ等でのトラブルが起こったりすることがあります。子どもたちには、自分で『善悪の判断』をしっかりし、悪いことは絶対しない『本当の勇気』をもち、悪いことを誘われても断る『強い気持ち』をもてるように育って欲しいと願っていますが、その為には、日頃から我々大人が子どもと色々なコミュニケーションをとる中で、子どものSOSのサインに気づいてあげる目を持つことも大切ではないかと思います。大人がアンテナを高く張りながら、『子どもの様子がいつも違うな、元気がないな、何か悩んでいる感じがするな……』という子どもの心の変化に気づいてあげて、困っている子どもへ「大丈夫?お母さん(お父さん)でよければ話を聞いてあげるよ」と声をかけてあげることで、一人で悩んでいる子どもを救う第一歩になると思います。

令和5年8月28日(月) 8/15(火)お盆に来た「台風7号」の被害はなかったですか?
ゆっくり過ごしたい「お盆」の時に、近畿地方を直撃した「台風7号」。予定していたことが中止になったり、予定を早めたりした方もいたのではないでしょうか?「台風が近畿地方を直撃する」とニュースが流れてくる中、私も含め、保護者のみなさんの脳裏には、5年前の9月4日に大阪湾を縦断した「台風21号」のことが蘇ってきたのではないでしょうか?大雨と風速50~60メートルの強風が吹き、様々なものが飛ばされ、壊され、今まで経験したことがないような甚大な被害が出ました。今回の台風7号はコースは少し違いましたが、同じように大阪湾を縦断する台風でした。私の知る限りでは、私たちの近くで5年前のような大きな被害はなかったように聞いていますが、みなさんは大丈夫だったでしょうか?私ごとになりますが、岸和田市内でも14日~15日にかけて台風接近による停電が何回か起こっていましたが、ほとんどが数分で復旧されていました。所が、私の住んでいる町内(岸和田市内)では、近くの高圧線に不具合が生じたのか、朝7時30分から夕方16時30分過ぎまでの9時間停電が続きました。台風接近に備えて懐中電灯、ラジオ、スマホ充電用のモバイルバッテリー、非常時の食事などは前もって用意していましたが、実際に長時間電気がない不自由な生活を経験してみて、『当たり前の生活ができることって、本当に有難いことや!』と痛感しました。うす暗い家の中でラジオを聞いていると「懐中電灯を天井にむけたら、部屋の中に光が広がるが、天井をむけた懐中電灯の上に、さらに水を入れたペットボトルを置くと、光が乱反射して周りを照らすことができ、簡単な『ランタン』が作れます」と聞こえてきました。実際やってみると、明るい光が拡散され光が広がることで、心の中も少し明るくなったような気がしました。

令和5年8月25日(金) 7月末、校務員さんが3年3組の床板の張替え作業を実施
夏休み中に、山直中学校区と山滝中学校区の校務員さんが本校に集まり、本校で劣化が1番はげしい3-3の床板の張替え作業を行ってくれました。毎年、市教育委員会の予算配当があった年に1クラス分の床板を購入し、夏休み中に床板の張替え作業を校務員さんがしてくれています。床板の劣化が進んでいる全クラスの張替え作業を一度にできたら理想的なのですが、1クラス分の床板でもかなり高額になる為、配当予算があった時しかできないのが現状です。張替え作業当日は、猛暑の中にも関わらず、手早く、きれいに仕上げてくれました。子どもたちも2学期からは、安全で綺麗になった床板の教室で、しっかり勉強してくれることと期待しています。

運動場や中庭、岡山門付近通学路の草刈り・・・
4年前までは夏休み最終日曜日に、PTA主催で「山北クリーン大作戦」(運動場の草ひき、校内清掃活動等)を行っていましたが、今は酷暑の為、行っていません。そこで8月17日に校務員さんと運動場や中庭、学年の畑周り、学校近くの通学路の草刈りをしました。特に岡山門を出て牛滝川へ向かう通学路は雑草が生い茂っていて、まむし等がいてもわかりにくい状態でした。昨年度、保護者の方から「岡山門を出た所の雑草が伸びて、通学路を覆っていて、川の近くでまむし等の心配もあるので、何とかなりませんか」とのご意見を頂き、所有者と学校で雑草を刈り、安心して通れる状態になりました。今年も台風通過後に、保護者の方から「岡山門近くの木の枝が折れて垂れ下り危険なので、切ってください。」とのご意見を頂き、早速撤去しました。子どもの安全を考えた貴重なご意見を頂き、有難うございました。
令和5年7月20日(木)1学期、ご理解・ご協力有難うございました。2学期も保護者の皆さんと学校が同じ方向を向き、子どもの成長を支えていけたらと思います。
1学期を振り返ると、5月8日からコロナ対応における国の基本的な考え方が変わったという点が一番大きな出来事でした。しかし、学校という集団生活の中では、どうしても密になってしまう場所や時間があり、そんな時には、マスクの着用や、手洗いの励行など・・・子どもたちが様々な場面で考えた行動を取ってくれたおかげで、コロナ感染の広がりもなく、無事1学期を終了することができました。有り難うございました。7月5日の校長室通信(第12号)にも掲載しましたが、暑くなり全国の海や川や池で悲しい水難事故が多発しています。山北校区内にも池や川や用水路が多くあり、危険な場所が点在しています。日頃から子どもたちには「大切な命を守るために、川や池には絶対に行かないように!」と指導していますが、今年の夏休みも暑い天気が続くことが予想されます。身近なところで悲しい水辺の事故を起こさないために、ご家庭でも池、川、用水路には絶対に行かない、近づかないようご指導をお願いします。そして、もし池や川や用水路で遊んでいる子どもを見かけたら、子ども達の大切な命を守る為に、ためらわずに毅然とした態度で注意をしていただくと共に、再発防止の為に学校や警察への電話連絡をお願いします。2学期も引き続き、コロナ感染予防・熱中症予防対策を意識しながら、授業参観、運動会、音楽会など、子ども達の頑張っている姿を通して、一人ひとりの成長を是非ご覧いただきたく思います。そして、ひたむきで一生懸命な子どもたちの姿から、子ども達の熱い思いと成長を受け止めていただき、保護者の皆さんに「感動・元気・パワー」を届けたいと思っています。

令和5年7月14日(金) 校長室前の「虫かご」の周りに、いつも子どもが ……
校長室の前にある「虫かご」の周りには、休み時間になるといつもたくさんの子どもたちが目を輝かせて集まってきています。この虫かごには、本校の浅田教諭(※)が子どもたちの喜ぶ姿を想像しながら、大事に育てている幼虫が入っていて、毎朝、その日に採った新鮮な葉っぱを入れてくれ、美味しそうに食べる幼虫の姿が見られます。子どもたちは目を輝かせながら、日々の成長を観察し、サナギが成虫になる素晴らしい瞬間に出会うこともありました。昨今、自然の中で生きている昆虫を見る機会がめっきり少なくなりましたが、目を輝かせて集まってくる子どもたちの姿を見ていると、保護者の皆さんの幼少期と何も変わっていなくて、「いつの時代も、生き物を見ている子どもの目は輝いているなぁ」と感じさせてくれます。 (※)浅田教諭は正門を入り正面左側にある学年の畑の世話もしています。

夏休み中の宿題における「生成AI」の取扱いについて
長期休業を迎えるにあたり、夏休みの宿題をする時における生成AIの取扱いについて、家庭において児童生徒が生成AIを使用することも想定されるので、不適切な使用が行われないように、学校での指導に加え、保護者に方にも理解を得るよう大阪府教育庁から依頼がありましたので、お知らせします。
★長期休業中の課題等についての留意点(文章作成の宿題にかかわるもの)
① 小学校段階の児童に利用させることは、特に慎重な対応を取る必要がある。
② 生成AIによる生成物をそのまま自己の成果物として応募提出することは、評価規準や応募規約によっては不適切・不正に当たり、学びが得られずこども自身のた めにならないことを、学校でも十分に指導すると共に、保護者にも周知し、十分理解を得ること。
★試行錯誤しながらも、自分の力で取り組むことが本人の成長につながります。安易に生成AIを利用させることのないよう、ご協力よろしくお願いします。
令和5年7月13日(木) 毎日、家庭学習をする習慣、身につけていきましょう !
学校で勉強したことをしっかり定着させる為には、学校から帰ったあとの家庭学習の習慣がとても大事とよく言われます。学校で勉強した時には理解していても、家で復習をしなかったら、時間が経てば学習した内容を忘れてしまって、確認テストでよい点数が取れない…ということがよくあります。毎日、家庭学習をする習慣がある子どもは、習慣がない子どもに比べて、復習テスト等での得点率が高いという分析結果もでています。そこで、本校では、家庭学習の習慣をつけるために、「自学ノート」の取り組みを進めています。また、山直中学校の中間・期末テスト期間にあわせて、小学生も中学生もテレビを消して、家庭学習をしっかりやろうという『すす勉ウィーク』という取り組みも行っています。そして、3年~6年の各学年で素晴らしい「自学ノート」を選び、三角屋根の掲示板や、会議室前の廊下窓や、各学年の掲示板に、すばらしい「自学ノート」を掲示しています。また、「3年生賞」「4年生賞」「5年生賞」「6年生賞」「すす勉大賞」を選出し、掲示しています。他の人のすばらしいノートを見て、「自分にもできるかも・・・私もがんばってみよう」という児童が一人でも増えてくれたらと願っています。保護者のみなさんも、懇談会等で学校へ来られた時には、三角屋根掲示板、会議室前廊下、学年掲示板にあるすばらしい「自学ノート」を、是非ご覧下さい。また、低中学年を中心に、教室前廊下に、一人ひとりが願い事を書いた「たなばた飾り」を置いています。かわいい願い事が多いので、是非ご覧ください。


令和5年7月5日(水) 悲しい水辺の死亡事故が……和歌山県日高川町で
7月1日(土)の午後、和歌山県日高川町高津尾の高津尾川で、父親と兄の3人で川遊びをしていた同町の小学4年生の男児(9才)が、下流に約100~200m流され、父親に救助されたけれど、心肺停止の状態で、その後死亡が確認された……という悲しい事故がありました。和歌山県内では、6月30日~7月1日にかけて降っていた雨により、川の水量が増えていたとみられ、いつもよりも高津尾川の水の流れは速くなっていたようです。「日頃は安全な川だから…」との思いで川遊びに行った時に、このような悲しい事故がよく起こっています。日頃から学校では、子どもたちに「大切な命を守るために、川や池には絶対に行かないように!と言い続けていますが、これから夏休みに入り、暑い日が続くことが予想されます。山直北小学校校区内にも池や川や用水路が多くあり、危険な場所が点在しています。我々の身近な所で、同じような事故がいつ起こっても不思議ではありません。このような悲しい事故を起こさないために、ご家庭でも池、川、用水路には絶対に行かない、近づかないようご指導をお願いします。また、池や川や用水路で遊んでいる子どもを見かけたら、子ども達の大切な命を守る為に、ためらわずに毅然とした態度で注意をしていただくと共に、再発防止のためにも学校や警察への電話連絡もよろしくお願いします。

「ヤングケアラー」をご存知ですか?
ニュースや新聞紙上等で大きな社会問題になっている「ヤングケアラー」。岸和田市教育委員会から「ヤングケアラーについての保護者向けのお知らせ」が届いています。右記にその内容を掲載しています。ご一読下さい。
【岸和田市教育委員会からのお知らせ】
「ヤングケアラー」とは、「一般的に本来大人が担うと想定されているような家事や家族の世話などを日常的に行っているため、子どもの権利が侵害されている可能性がある18歳未満の子ども」のことを言います。もちろん、ご家庭での役割として子どもが家族をケアすることは、思いやりや責任感を育むことにつながるなど、良い面がたくさんあります。一方で、年齢や成長に見合わない責任や負担を負うことで、子どもの成長や学習に影響が出るとも言われています。
○ヤングケアラーの例(一般社団法人日本ケアラー連盟「こんな人がヤングケアラーです」より抜粋)
 障がいや病気のある家族に代わり、買い物・料理・掃除などの家事をしている
障がいや病気のある家族に代わり、買い物・料理・掃除などの家事をしている
 家族に代わり、幼いきょうだいの世話をしている
家族に代わり、幼いきょうだいの世話をしている
 目を離せない家族の見守りや、声かけなどの気づかいをしている
目を離せない家族の見守りや、声かけなどの気づかいをしている
令和5年6月30日(金) 明日7月1日は、151回目の創立記念日
明日7月1日(土)は、岸和田市立山直北小学校・幼稚園の151回目の創立記念日です。昨年度は150回目の記念すべき年でしたが、コロナ感染予防を最優先に考え、地域の方や保護者の方を来賓としてお招きしての記念祝典は実施せず、その代わりに、児童・園児のために役立つものを購入したり、学校園の記念になる物品を残したりしました。(150周年記念新聞、記念下敷き、正門前掲示板、PTAスリッパ、教室・特別教室・体育館へさすまたの設置等)全国的に子どもの出生数が減り、大きな社会問題になっていて、岸和田市内でも同様の状況が見られます。ただ、山直北小学校区内の0~5才児の人数推計をみると、どの年代も100人程度の子どもが校区内に住んでいて、今とあまり増減がない児童数(学級数)が維持できそうな状況です。
【山直北小学校・幼稚園の歴史】
山直北小学校の創立記念日は、明治5年(1872年)に「郷学校」(村の学校)を設立した日を記念として定められました。
●《新在家校》明治5年7月1日 新在家に「郷学校」を設立する(創立記念日)田治米正源寺本堂を校舎にする。
明治8年4月 校舎を新在家円満寺本堂に移転する。 明治8年5月 名称が新在家小学校となる。
《三田校》 明治7年4月 三田小学校ができる。正楽寺本堂を校舎にする。
●明治41年4月1日 新在家校と三田校が合併して「山直尋常小学校」となる。
●昭和10年11月1日 山直上村と山直下村が合併して山直町ができる。その為、校名を変更し「山直北尋常高等小学校」となる。
●昭和12年8月10日 講堂竣工式挙行(野上和三郎氏寄贈)
●昭和16年4月1日 国民学校令施行により「山直北国民学校」となる。
●昭和17年4月1日 岸和田市と合併し「岸和田市立山直北国民学校」となる
(昭和20年8月15日終戦)
●昭和22年4月1日 学校教育法施行により「岸和田市立山直北小学校」となる
(このあと、鉄筋校舎が次々と新築されました)
●昭和48年4月1日 校区変更により、城東小学校へ2年生の一部転校
●昭和49年4月1日 校区変更により、城東小学校へ4年生の一部転校
●昭和50年4月1日 校区変更により、城東小学校へ6年生の一部転校
●平成4年6月4日 講堂(昭和12年、野上和三郎氏寄贈)と木造校舎のお別れ式があり、解体される。
●平成5年10月17日 体育館と鉄筋2階建8教室並びに多目的室2教室が新しく建てられ、現在に至る。(今の1・2年生の教室棟)
●平成のあいだに、給食室移設工事竣工・トイレ改修工事。教室空調設備工事などを行い、今に至る。
●令和5年10月には、非常変災時避難所となる体育館にエアコンが設置される。
●学校に「郷土誌 山直」という立派な本があります。その本によると・・・・・・
昭和7年から11年にわたって、当時の校長・宇野主也先生が編集された本です。それによると、古くは「山直は、山部の直(アタヘ)の後なり」とあり、地方を統一した者の名前に由来し、由緒ある「山直郷」となったとも言われています。「山直郷」は山直上村と山直下村があり、山直下村〈三田、摩湯、今木、東大路、田治米、新在家(岡山)〉が山直北小学校の元々の校区でした。
●このように古い歴史を持つ山直北小学校の「学校沿革誌」には、児童数が掲載されており、下記のように児童数が推移しています。
=児童数= 明治41年度( 347名) → 昭和 元年度( 561名) → 昭和48年度(1348名) → 昭和55年度(1274名) → 平成20年度(1029名) → 令和 5年度( 648名)
1回目のピークは昭和48年の1348名、次のピークが昭和55年の1274名で、市内で規模が1番大きい時代が長く続きました。しかし、ここ数年は児童数が徐々に減少していることもあり、今は常盤小、光明小に次いで市内で3番目の規模になっています。明治5年の創立以来、令和5年3月までに16,313名が山直北小学校を卒業していきました。長い歴史と伝統がある本校は、たくさんの地域の方に愛され、みなさんの思いが詰まっている学校です。これからもその思いを大切に受け継いでくれる子ども達を育てて参りたく思います。今後もご理解・ご協力をお願い申し上げます。

令和5年6月16日(金) 6/14(水) 2回目の「引き渡し訓練」を終えて
6月14日(水)児童の待機場所を体育館に想定して、13:45~14:00の時間帯での「第2回引き渡し訓練」を行いました。平日のお忙しい時間帯にも関わらず、全家庭数495軒の内、195軒(39.4%)の方がお迎えに来てくれました。たくさんの方のご協力を賜り、有難うございました。昨年の11月は児童が運動場で待機する想定で行い、今回は児童が体育館で待機する想定の訓練でした。課題もあったかと思いますが、予想していた以上にスムーズに進んだように思います。①近い将来起こる可能性が高く、家・電柱・建物が倒壊するかもしれない『東南海沖地震』等の大地震時や、②殺人犯などの凶悪犯が山北校区内に潜伏している可能性がある時などの非常時は、命の危険があるので児童だけで下校させることができないため、速やかに保護者の方に来ていただく想定で行っています。本当に非常時が起こった時は、保護者の方が一度にたくさん来られ、保護者の方も教職員も緊張感が高い中で、訓練時のような落ち着いた心理状態で対応できるのか?また、地域の方が避難所として学校に来るかもしれないし、学校周辺の建物や校舎の倒壊等も想定されるので、今回の訓練をベースにして、その時々の状況に応じた臨機応変な対応の必要性も感じる良い機会になりました。今回の訓練を通して、保護者の目線で、「本番に向けて、ここは〇〇したら、よりスムーズにできるのでは…」等のご意見がありましたら、遠慮なく伝えていただけたらと思います。


令和5年6月14日(水) 図書室に15万円分の図書の助成が!~元朝会教育振興基金~
「元朝会教育振興基金」とは、岸和田市を中心とした地域の学校における教育振興に役立てて欲しいとの寄付者(個人や企業等)のお志を尊重して設立されたもので、岸和田市内の学校に図書の購入助成をしてくれています。毎年、市内の数校に助成をおこなってくれていて、本年度は山直北小学校に購入助成をしてくれる年にあたっています。図書担当の中嶋教諭と久納学校司書が中心となり、本校の図書室にはない図書で、子どもたちが興味を持って、楽しく読んでくれそうな15万円分の図書を選定してくれ、先日図書室に本が届きました。ワクワクドキドキしながら本を読むことで様々な想像をしたり、新しいことを知ったり、考えを深めたりすることができ、子どもたちの想像力や夢を育んでくれることと思います。また夢中になるひとときや、くつろいだ時間を過ごすことで、本を読む時間が心の支えになることもあるかと思います。今回購入した本を読んだ感想を、子どもたちから聞いてみたいものです。

牛滝川にかかる「おまつ橋」の落書き。消去し綺麗な状態に
山直中学校の運動場近くにある「おまつ橋」の内側にいつからか落書きがありました。「余りに見苦しいので、何とか綺麗にできませんか…」と大阪府土木事務所に相談した所、関係者が見に来てくれ、ペンキを塗りきれいな状態にしてくれました。きれいな状態なら落書きもできないけれど、汚い状態のままなら、どんどん落書きが増えていく……というのは、よくある光景です。「おまつ橋」の近くを通りかかったら、一度ご覧ください。

令和5年6月2日(金) 6/14(水)5限目の「第2回引き渡し訓練」に向けて
児童だけでは下校させられないような非常変災が起こった時等(電柱や建物が倒壊する等の大災害時や、殺人犯等の凶悪犯が校区内に潜伏している時)に備えて、保護者のみなさんに学校にお迎えに来ていただく「第1回引き渡し訓練」を、昨年度は運動場で11/4(金)に実施しました。その時は全校児童の約44%の保護者の方がお迎えにきていただきました。今年は非常変災等が起こった時に、体育館での引き渡しを想定して実施します。非常変災時は、全校児童が素早く、一斉に体育館に集まることが大切なので、5/30(火)1限目に集まる練習をしたところ、子どもたちは無駄な動きをせずに、短時間で体育館内に集合することができました。今回の第2回引き渡し訓練も平日の午後になりますが、可能な範囲でご理解・ご協力をお願いします。

6年音楽会(6月⇒11月)、学校水泳(6~7月⇒9月~12月)
【変更①】昨年度までは、6月学習参観時に6年音楽会を、11月学習参観時に5年・4年音楽会を実施していましたが、本年度からは3つの色別にわけた4~6年生の音楽会として11月30日に実施します。低学年の児童も高学年の音楽会を見ることで、「自分もやってみたい」と憧れを持ってくれたらと思います。
【変更②】6月下旬から7月初旬にかけて山北プールで行っていた「学校水泳」ですが、プールの老朽化に伴い、市教育委員会主導で民間業者(ザ・ビッグスポーツ)に水泳指導を委託し、9月から12月にかけて、学年ごとに期間を集中して各4回ずつ実施する予定です。(なお、幼稚園は3回で、7月実施予定です)
※どちらも、日時や内容の詳細が決まり次第、早めにお知らせいたします。
令和5年5月31日(水) 「継続は力なり」毎日の家庭学習を続けていますか?
●4月、市教育委員会から「家庭学習のてびき ~自分磨きの達人へ~ 」のリーフレットが配布されています。是非、お子さんと一緒にご一読ください
家庭学習の大切さ① → 家族の協力で「環境づくり」を
★家庭で学習する時間を「宿題」+「自主学習」する時間と考え、子どもたち一人ひとりに「学習習慣」を身につけさせ、わかる喜びや楽しさを味わえるようになれば、学習意欲や自信が高まります。「自主学習」は何か特別な学習をするのではなく、復習や予習をする時間と考えたらいいと思います。
★家庭学習を定着させるには、「学習に集中できる環境づくり」が大切です。例えば、①始める時間を決める ②学習する場所を決める ③テレビ等を消し、机等の上を広くしてから始めるなど、家族の協力が必要になってきます。毎日の予定にあわせて、集中して学習できる時間を整えましょう。
家庭学習の大切さ② → ほめる 見守る 励ます
★子どもたちの家庭学習に目を通し、以下の3点(◎印)をほめたり、励ましたりすることで、自信を持たせ、やる気を引き出しましょう。小さな変化でも積み重ねれば、大きな変化です。◎自分で家庭学習をしたこと ◎計画通りにしたこと ◎継続したこと 等
上記の①②を実行し、つづける → 家庭学習の効果(良さ)
・学習習慣が身につく ・学習意欲、自信が高まる ・脳が活性化する ・計画的にする力(予習復習)がつく ・学校で習ったことを忘れない ・学力、考える、工夫する、創造する、追及する力がつく ・約束を守る力(するべきことをする力、決めたことをやり遂げる力)が育つ ・テレビやゲームの誘惑に負けない力・我慢する力がつく ・根気 ・自分をコントロールする力がつく ・子どもの理解度がわかる。 ・家族のふれあいや会話の機会が増える
令和5年5月25日(木) 熱中症対策、十分な量の水分を持たせて下さい!
例年に比べると、今年の5月は湿度が多いジメジメした日が少なく、乾燥した心地よい風が吹き、過ごしやすい日が続いています。ところが6月になると、急に湿気が多く、ベタベタ感が体にまとわりつくような梅雨の時期を迎えます。そして8月末までの夏季の間は、高温多湿で不快感が高い天気が続きます。教室ではクーラーをつけながら、外に出る時は必ず帽子をかぶり、常にこまめに水分補給するよう児童に指導しつつ、熱中症予防に注意を払っています。5月8日以降はマスクをはずす児童も徐々に増えてきていますが、「今はマスクを外していいと思うからはずす時、今はつける方がいいと思うからつける時…」と、自分で考えてマスクの脱着をしている児童もたくさんいます。学校では、体育の授業時や外遊び登下校時などの熱中症の恐れがある場所では、熱中症予防を最優先に考えてマスクをはずそうという指導をしています。また、今までは涼しかったため、たくさん水分を取らなくても過ごせる日が多かったのですが、今後はかなり暑くなる日が増えてくると思われます。登校時から家に帰るまでの間、お茶(水)を飲む機会が大幅に増えるので、家に帰った時にお茶(水)が残っているくらい、十分な量が入る大きめの水筒を持たせていただきますようよろしくお願いします
5/19(金) 雨の中の春の遠足、ルールを守って・・・
子どもたちが楽しみにしていた春の遠足、当日は雨が降り、どこへ行ってもたくさんの人(同じ日に遠足に行った学校、修学旅行で関西に来ていた学校、コロナ対応緩和で来日した外国人など)がいて、当初の予定通りの行動ができない学年もありました。ただ、「遠足」という学校を離れての活動を通して、クラスメイトとの楽しい思い出を作ると共に、集団活動時のルールを守る大切さ、教室では見ることができない友だちの良い面を知る機会、同じ場所を訪れている方への気遣いなど・・・たくさんのことを学べた学習の場にもなったことと思います。
令和 5年5月18日(木) ◎児童朝会で「今年の児童会目標」を紹介しました
「や」=やるからには 「ま」=まけないで 「き」=きしわだいち 「た」=楽しい 山直北小学校
5月16日(火)の児童朝会で、児童会の人たちが「や」「ま」「き」「た」を使った「令和5年度児童会目標」を紹介してくれました。「やるからには 負けないで 岸和田1楽しい山直北小学校」とても頼もしいスローガンで、やる気が伝わってきます。今年の児童会も6年生の6人を中心に、下級生12人(5年生と4年生、それぞれ6人ずつ)を引っ張ってくれながら、1年間一緒に活動をしていきます。
今年はコロナ禍による活動制限が大幅に緩和されたので、昨年までとは違った新しい活動ができると思います。みんなで知恵を出し合って、素晴らしい児童会活動を行ってくれることを期待しています。
「命にかかわることなので、注意喚起をしてあげて!」
5月11日(木)夕方、地域の方(学校協議会委員)に学校に来て頂き、地域の方から見た子どもの様子についての意見交換会をしました。その中で①毎年、牛滝川近辺に「マムシ(へび)」が出没し、かまれたら猛毒で死亡してしまうこと ②川や池で遊んでいる子どもが、足元が滑り深みに引きずり込まれ、溺れてしまう死亡事故など、この時期によくある事故を心配してくれていました。「命にかかわる大事なことで、事故が起こってからでは遅い。未然防止の視点で、できるだけ早く全校児童に注意喚起をしてあげて!」というお声をいただきました。そこで、5月16日の児童朝会時、「マムシ」の特徴がわかる写真や「水難事故」の動画を見せながら、注意喚起を行いました。池などで遊んでいる姿を見かけたら、迷わず注意をお願いします。
令和5年5月15日(月) 4/28(金) 運動場での対面式+児童朝会
1年生が入学して約3週間が経ち、2年生~6年生との「対面式」を約4年ぶりに運動場で実施しました。久しぶりの運動場での児童朝会だったので、どの辺りに並べばいいのか?並ぶ順はどんな順番?など・・・4年前は当たり前にできていたことができなくなっていました。一度経験があれば自信をもってできることでも、経験をしていないからできない・・こんなことは世の中に一杯あります。子どもたちは学校という集団生活の様々な場で、失敗体験や成功体験を重ねて、生きていく上で必要な大事なことをたくさん学び、成長していっています。
5/12(金) 色別結団式を実施。成長の跡が・・・
全校児童が1組~3組がそれぞれの色の3つの集団で集まり、6年生が中心となって、楽しいゲーム等を進行する「色別交流会」という時間があります。日頃は人前で話をするのが苦手な6年生も、下級生の前に立ち、説明をする役割を任されたら、「こう言ったら1年生も分かるかな!?」とか、色々考えて本番に向けて練習をします。そして本番、「緊張して少し失敗したけれど、80点位かな?次こそは」と初めての経験を通して、失敗からの学びと、「できた!」という成功体験を通し、「できる」という自信をつけていくと思います。家の中でも、大人がやればば早いことでも、大人が見守りながら子どもにさせることで、「ありがとう」の声かけが増え、その経験を通して子どもに多くの学びや成長の跡が見られることがあります。「うちの家には、子どもに任せて、子どもが経験から学べる場面があるかな?」と、一度振り返ってみて下さい。もし無いなら、子どもと相談しながら、学年に応じた学びにつながる経験を是非させてあげていただけたらと思います。

令和5年4月28日(金) 暑くなってきたら、水辺の事故が多発しています……
① 昨年、新学期が始まって間もない4月11日の放課後、大阪府枚方市の小学生男女5人が池の西側で遊んでいた時に、8歳の男児が池ののり面ですべり、溺れそうになったところ、10歳の男児が助けようとして池にはいり、溺れてしまいました。池の周囲にはフェンスがありましたが、小学生が「立入禁止」の防護柵を乗り越えて遊んでいました。最初にすべった児童は自力で這い上がり、助けようとして池に入った男児が溺れてしまい意識不明の重体…という痛ましい事故が起こってしまいました。多くの池ののり面には、危険を回避するための足場を確保できるようなコンクリートブロックが敷き詰められています。しかし、ブロックの水面下はこけや泥がこびりつき、ヌルヌルしていてとても滑りやすくなっています。池にはまってしまったら這い上がろうとしても滑ってしまい、子ども・大人に関係なく、簡単には這い上がれない、そのようなとても危険な場所です。
② 5年前の5月には、滋賀県甲賀市で複数の上級生と集団下校途中の小学1年生の女児が、幅45cm×深さ45cmという普段なら危険を感じない側溝で、水に足をつけて遊んでいた時に転落し、増水により流され死亡した…という悲しい事故が起こってしまいました。
山直北小学校校区内にも用水路や池や川が多くあり、危険な場所が点在しているので、我々の身近な所で同じような事故がいつ起こっても不思議ではありません。このような悲しい事故を起こさないために、ご家庭でも用水路や池、川には絶対近づかないようご指導をお願いします。また、池や川や用水路で遊んでいる子どもを見かけたら、子ども達の大切な命を守る為に、ためらわずに毅然とした態度で注意をしていただくと共に、再発防止のためにも学校や警察への電話連絡もよろしくお願いします。
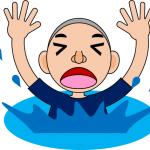
令和5年4月26日(水) ◎もしもの時に備え、「心肺蘇生」への意識を!
何らかの理由で児童や教職員が心肺停止状態になってしまった時に備え、「AED」を小学校と幼稚園(今年から)に設置しています。心肺停止状態という緊急事態は起こって欲しくありませんが、いつ、どこで、起こるかわかりません。もし、自分の目の前で起こった時に備えて、自分が素早くどんな対応をしなければならないかを意識しておくことが大切です。
山直北小の本館校舎の入り口にAED(除細動器)があります


自分の目の前で、病気やケガにより、突然心肺停止、又はこれに近い状態になった人が倒れた時は、次の①~③の対応が重要です。
① 何の迷いもなく、近くにいる人への適切な指示(119番通報とAEDを探すこと)を出すこと。
② 1秒でも早く「心肺蘇生」を行うこと。「心肺蘇生」を行えるかどうかが、倒れた方の蘇生率や社会復帰に大きく影響してきます。心肺停止状態の人に対し、心臓マッサージのための胸骨圧迫、及び人工呼吸を行うことを「心肺蘇生」と言います。人間が生きている限り、体の全ての細胞はいつも酸素を必要としています。心肺停止状態となり脳に酸素が供給されない状態になると、直ちに脳の神経細胞の機能に重大な変化が起こり始め、そのまま放置すると死に至ります。脳が酸素無しで生きられる時間はわずか3~4分と言われています。そのため、その場に居合わせた人による適切な救命処置の有無が傷病者の命を大きく左右してきます。救急車の到着を待つ間、居合わせた人がすぐ「心肺蘇生(胸骨圧迫)」を始めると、救命率が2~3倍増やすと言われています。また、「心肺蘇生」で脳に酸素を送り続けることにより、後遺症が残る確率も下がります。
③ 「AED」が届いたらすぐに電源をいれ、音声メッセージに従って操作をし、「電気ショックが必要」と音声で指示がでたら、ショックボタンを押すこと。そして、救急車が到着する迄「心肺蘇生」と「AED」を繰り返します。また「心肺蘇生」はかなり疲れるので、交代する人がたくさんいたら、長く続けることができます。インターネット上に「心肺蘇生の手順」が詳しく載っていますので、一度は確認をしておいてください。
本校でも土日に学校施設開放に登録している地域の団体(児童や大人)が、運動場や体育館を使用しています。その時、心臓発作等で急に倒れた人がいた時、救急車が到着するまでの数分間に、適切な「心肺蘇生」と「AED(除細動器)」を行えたら大事な命を救うことができると考え、3年前から三角屋根下の校舎入口近くの壁面に「AED」を移動しました。(いざという時にすぐに使わないといけないので、施錠はしていません。)大切な人の命を救う大切なものなので、保護者の皆さんも来校時に三角屋根下の校舎入り口近くの壁面にあるAEDの設置場所を一度は確認しておいて下さい。
●岸和田市内でも過去に下記の心肺停止事例がありましたが、その場に居合わせた人達が素早く適切な対応をした結果、今も元気に過ごしています。
①高校野球の練習試合中に打者が打った硬球が投手の胸部を直撃し、心肺停止状態になったが、観客に救急救命士が居合わせ、すぐに「心肺蘇生」を行い、「AED」も併用しながら救急車の到着を待った。そのおかげで投手は元気に復帰できた。
②だんじり祭りの時に心肺停止で急に人が倒れた。その時は「AED」が近くになく、救急車の到着にも時間を要したが、祭礼関係者に看護士が数名いて、救急車が到着するまでの間、交代で「心肺蘇生」を行った。そのおかげで、後遺症もなく、無事社会復帰できた。
令和5年4月10日(月) 令和5年度 全校児童644名でスタートしました
校門の桜の花や校庭のチューリップ・パンジーの花が満開に咲き誇る中、4月6日(木)に入学式があり、94人のかわいい1年生が入学してきました。前日の5日には新6年生が登校し、入学式の準備を行ってくれました。テキパキと作業をしてくれたおかげで、スムーズに準備が進みました。ありがとう!「何事にも一生懸命頑張り、下級生の良き手本となってくれる」そんな山北の最上級生の良き伝統を、しっかり受け継いでくれていることをとてもうれしく思い、「さすが6年生!」と感心しました。
4月以降のコロナ対応の変化
①校内でも、マスクの脱着は個人の意思に委ねられることになります。マスクをはずしている人もいれば、まだまだコロナ感染への不安がある・基礎疾患がある・高齢者の方と同居している・花粉症でマスクをつけていたい……など、様々な理由でマスクをつけている人もいます。マスク脱着への一人ひとりの思いを大事にしつつ、全ての人が快適に過ごせる学校生活になればと願っています。 ②学校はたくさん児童が集団生活を送る場所なので、感染予防のために必要な適度な距離が保てない環境下での教育活動に関しては、感染予防のための行動制限が残っています。ゴールデンウィーク明けの5月8日(月)以降は、2類から5類に移行されるのに伴い、学校教育活動の行動制限もかなり緩和されることが予想されます。ただ、それまでは従来の感染予防を行いながらの教育活動を実施して参りますので、ご理解・ご協力よろしくお願いします。詳細がわかり次第、メールやお便り等でお知らせ致します。


令和5年3月24日(金) 1年間、ご理解・ご協力を賜り、有り難うございました
3月16日(木)の卒業式当日は天気にも恵まれ、「第150回山直北小学校卒業証書授与式」を挙行することができ、129名が巣立っていきました。今年度もコロナ禍で密を避けるために、来賓の方を招待することができず、保護者2名以内と制限がある中でしたが、129名のそれぞれが立派な決意表明をおこない、素晴らしい卒業式を作り上げてくれました。そして、今日は1年~5年の修了式を迎えました。1年前にはできなかったことが、この1年間でできるようになり、一人ひとりそれぞれが心も体も成長し、良い意味でお兄さん、お姉さんになったように思います。おうちでも「1年前に比べて、こんなことができるようになったね」と、子どもが頑張ったことをほめてあげていただけたらと思います。4月1日からは、マスクの脱着が個人の意思に委ねられ、それぞれの考えの中でマスクをつける人もあれば、マスクをつけない人もいるようになります。マスクの脱着の有無にかかわらず、子どもたちがお互いの気持ちを尊重しながら、一人ひとりにとって楽しい学校生活が送れればと願っています。ただ、今まで行ってきた感染予防のための健康観察、手洗いなどについては、4月1日以降も引き続き行うことになっていますので、ご理解・ご協力をお願いします。
この1年間、保護者の皆様には、コロナ禍の中、学校行事等で様々な変更があったにも関わらず、ご理解・ご協力を賜り、本当に有難うございました。明日から16日間の春休みに入りますが、手洗い、うがい等の感染予防は継続していただき、自転車の飛び出しによる交通事故にも気をつけながら、楽しい春休みを過ごして下さい。
令和5年3月10日(金) 「継続は力なり」毎日の家庭学習、続けていますか?
●3月中に、岸和田市教育委員会から「家庭学習のてびき」(~自分磨きの達人へ~)のリーフレットが配布されます。お子さんと一緒にご一読ください
家庭学習の大切さ① → 家族の協力で「環境づくり」を
★家庭で学習する時間を「宿題」+「自主学習」する時間と考え、子どもたち一人ひとりに「学習習慣」を身につけさせ、わかる喜びや楽しさを味わえるようになれば、学習意欲や自信が高まります。「自主学習」は何か特別な学習をするのではなく、復習や予習をする時間と考えたらいいと思います。
★家庭学習を定着させるには、「学習に集中できる環境づくり」が大切です。例えば、①始める時間を決める ②学習する場所を決める ③テレビ等を消し、机等の上を広くしてから始めるなど、家族の協力が必要になってきます。毎日の予定にあわせて、集中して学習できる時間を整えましょう。
家庭学習の大切さ② → ほめる 見守る 励ます
★子どもたちの家庭学習に目を通し、以下の3点(◎印)をほめたり、励ましたりすることで、自信を持たせ、やる気を引き出しましょう。小さな変化でも積み重ねれば、大きな変化です。 ◎自分で家庭学習をしたこと ◎計画通りにしたこと ◎継続したこと 等
上記の①②を実行する → 家庭学習の効果(良さ)
・学習習慣が身につく ・学習意欲、自信が高まる ・脳が活性化する ・計画的にする力(予習復習)がつく ・学校で習ったことを忘れない ・学力、考える、工夫する、創造する、追及する力がつく ・約束を守る力(するべきことをする力、決めたことをやり遂げる力)が育つ ・テレビやゲームの誘惑に負けない力・我慢する力がつく ・根気・自分をコントロールする力がつく ・子どもの理解度がわかる。 ・家族のふれあいや会話の機会が増える
令和5年3月6日(月) 3月4日(土)「ストップマーク」の補修作業を実施
山北校区内は細い路地が多く、歩行者や自転車の車道への急な飛び出しによる交通事故が起こる可能性が高く、交通事故未然防止の為に、地面にたくさんの「ストップマーク」をひいてあります。また、最近は信号の影響を受けない山北校区内のさまざまな道(岡山公園⇔和田病院前、岡山公園⇔岡山交差点、三田郵便局⇔三田町内、日本鋼管前⇔田治米町内等)が和泉市や尾生町方面への抜け道にもなっていて、朝は通勤で急いでいるたくさんの車が通行しています。子どもたちはその道を横断して、町内の安全な細い道を歩いて登校しています。岸和田警察署の交通課(?)がひいたマークもありますが、それだけでは十分ではないので、毎年3月の第一土曜日の午前中にPTA実行委員(生活環境委員)やPTA役員、教職員が集まり、校区内を一緒に歩いて回り、消えかけている箇所にラッカーをふきつける「ストップマーク」の補修作業をしています。昨年はあいにくの雨で作業ができず、春休み中に教職員で手分けして行いましたが、今年は快晴のもと、校区内を一緒に歩きながら作業を行うことができました。ご参加いただいた保護者のみなさん、一緒に参加してくれた子どもたち、本当にありがとうございました。このマークのおかげで、交通事故が防げたらと願っています。また、「今はマークをひいていないけれど危険だな」と思う箇所や、まだマークが消えかけている箇所がありましたら、学校へご連絡をいただけたらと思います。よろしくお願いします。


令和5年3月3日(金) 2/24(金)と3/1(水) 3年ぶりに「6年生を送る会」
3年前までは、2月末に全校児童が体育館に集まり、もうすぐ卒業していく6年生に、1年生~5年生が学年ごとに感謝の気持ちを伝える「6年生を送る会」を実施していました。コロナ禍の2年間は、体育館に集まることができない為、「6年生を送る会」に代わるものを5年生が中心となり企画・立案し、1年生~5年生のみんなで6年生全員への贈り物を作製しました。そして、5年生が在校生を代表して6年生一人ひとりに6年生の教室で贈り物を手渡すというセレモニーをしていました。今年は、コロナ感染予防も少しずつ緩和されてきているので、1年生~6年生が3つの色別ごとに体育館にあつまり、色別による「6年生を送る会」を実施しました。どの学年も、どうしたら6年生に感謝の気持ちを伝えることができるかをしっかり考えて、一生懸命「感謝」の気持ちを込めた出し物をしてくれました。今まで色別活動等でたくさんの関わりがあった下級生からお礼の言葉や感謝の言葉を直接伝えられた6年生は、きっとたくさんの思い出が走馬灯のようによみがえってきたのではないでしょうか。コロナ禍で厳しい制限があった時期にはできなかった『直接会って感謝の思いを伝えあうこと』が、今回できて本当によかったと思います。


第150回「卒業式」 6年生の体育館練習が始まる
3月1日(水)3限目、5年生全員で体育館内のシート敷きと椅子ならべをしてくれました。そして4限目に6年生が体育館に入り、3人の学級担任の先生から、卒業式を迎えるにあたって大事にして欲しい思いを子どもたちに伝えてから、式練習がスタートしました。小学校生活最後の授業である「卒業式」にむけて、毎日2時間ずつの練習があります。本番に向けて頑張っている6年生の子どもたちに対し、ご家庭でもご支援よろしくお願いします。
【令和5年3月3日より、「校長室より③」の新設について】
令和2年4月に「校長室より①」を新設し、掲載をしてまいりましたが、令和3年7月21日に私が間違えてパソコンのボタンを押してしまった為、従来の「校長室より①」の続きに入力ができなくなってしまいました。色々試みたのですが、令和2年4月以降の今までのデータがすべて消えてしまうことになることが判明し、令和3年9月30日に「校長室より②」を新設いたしました。以後順調にいっていたのですが、令和5年3月1日に過去と同様の操作まちがいをしたため、「校長室より②」の続きに入力ができなくなってしまいました。色々試みたのですが、続けて入力すると今までのデータがすべて消えてしまうことになることが判明し、令和5年3月3日に「校長室より③」を新設いたしました。今後もよろしくお願いします。